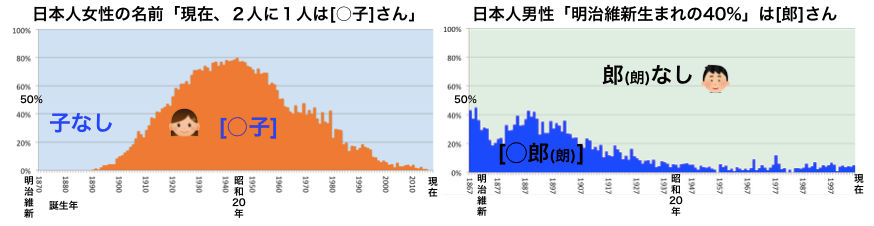(12) 日本中が涙した小説のヒロイン「浪子」(1898)
12-1 1900年に出版された『不如帰』
私は、いつものように、分厚い『明治ニュース事典』①〜⑧ (毎日コミュニケーションズ1983-86)を開いて、[子]のつく名前を探していました。そのとき,1898(明治31)年に[浪子]という名前を見つけたのです。
[浪子]は、徳富蘆花の書いた『不如帰』という小説の悲劇のヒロインです。1898(明治31)年11月から翌年5月まで『国民新聞』に連載され、1900(明治33)年1月に単行本として出版されます。『不如帰』はベストセラーとなり「明治の小説で、最初に百版を記録」(*1)し、「芝居」「活動写真」「流行歌」にもなり、「英語」や「フランス語」にも翻訳された(*2)といいます。徳富蘆花のことを「明治全期を通じて最大のベスト・セラー作家」(*3)と書く本もあります。その蘆花の最大のベスト・セラーが『不如帰』です。
この話は、実際にあった話をもとにしています。大山巌元帥(妻は捨松→華族の女性たちと[子])の娘が死んでしまうまでの実話(スキャンダル)を小説にしたものです。
(あらすじ)浪子は、海軍少尉男爵の小島武男と結婚する。しかし、結核にかかってしまう。夫の母(姑)は、息子に無断で、そんな浪子を離縁してしまう。浪子は、武男をしたいつつ、死んでいく。
浪子のライバルとして「お豊」という女性も登場してきます。お豊は、取引業社の娘で、不細工で品のない女性(悪役)として描かれています。浪子が上品でおしとやかに描かれているのと対照的です。
(*1)木村毅(1969)「徳富蘆花入門」『豪華版日本現代文学全集5徳富蘆花』講談社、p.397
(*2)同上
(*3)瀬沼茂樹(1965)『本の百年史 ベスト・セラーの今昔』出版ニュース社、p.77
12-2 本当に『不如帰』という小説が時代を変えたか。
ただ気になるのは、「浪子」は華族の娘です。庶民は、そんな華族を真似して、娘に[子]をつけるでしょうか。
こんな証言がみつかりました。徳富蘆花が死んだとき『婦人公論』(中央公論社,1927年11月号)が特集記事「不如帰座談会」を掲載します。その参加者は「山川菊栄」「岡本かな子」など大物女性10名です。その中から引用します。
若杉鳥子.........私は子どものとき、まだ恋愛なんていうものがさっぱりわからない時分に、知っている芸者に借りて読みました。12才ぐらいでした。
山田邦子.........私は14位の時でした。看護婦をしている人から借りました。何しろ病院の寄宿舎の看護婦が一晩皆泣かされたという話を聞いて。
吉屋信子.........当時の一般上流の人々にも、下流の子どももおかみさんにも、必ずどこかに触れるセンチメンタルがあるんじゃないですか。それで上中下こぞって(読まれたのです) ( )は筆者が補足
つまり、当時の多くの人々は、「浪子」が自分に乗り移ったかのように泣きながらこの小説を読んだのです。しかも吉屋信子(1896-1973)の証言によると「当時の一般上流の人々」も「下流の子どももおかみさん」もこぞって自分のことのように読んだのです。
またこんな証言もあります。田山花袋(1872-1930)の「明治名作改題」『小説作法』(1909)博文館(p.236)からです。(初出は『文章世界』1907(明治40)4月1日号、博文館)
およそ明治の小説中、この作ほど世に歓迎されたものは恐らく有るまい。上流中流下流の三社会、みなこれを読まざるなく、浪子の悲しい運命に涙を注がぬものはない。ことに、これを劇に仕組んで、至るところに喝采を博した。かく喝采されたのはその材料と実感と同情とによるのであろうが、とにかく流行小説の大関たることは争はれぬ。
(「大関」とは「同類の中でもっとも傑出したもの」小学館『日本国語大辞典』1993)
田山花袋は、『文章世界』という雑誌の編集代表で、その人が同時代(1907年)に『不如帰』を「明治の小説中、この作ほど世に歓迎されたもの」はないと言っているのです。

瀬沼(1965)は「徳富蘆花の『不如帰』とならび称される作品に尾崎紅葉(1867-1903)の『金色夜叉』がある」(瀬沼茂樹『本の百年史』(出版ニュース社1965)と言います。『金色夜叉』は、1897(明治30)年から1902年にかけて『読売新聞』に連載されました。その主人公「お宮」は、ダイヤモンドに目がくらみ恋人を捨ててしまう女性です。恋人の貫一は金の亡者(金色夜叉)になってしまいます。残念ながら尾崎の死去で、その作品は未完成になってしまいました。
『不如帰』の「お豊」といい、この「お宮」といい、どうも当時の「お◯]という名前の人物は印象が良くありません。「古い女」というイメージです。『不如帰』の「浪子」は対照的で、清楚で「新しい女」です。
それでは、明治の世の中(1900年頃)では、いったいどちらが多く受け入れらてたのでしょう。
藤井は、「『不如帰』がつきつけて見せたいくつかの課題ー戦争・結核・家族制度などー」が「読者にとっての切実な問題」となっていた、と書く。特に「結核」は不治の病であり、当時の日本人一人一人につきつけられた課題であった。
そしてその解決が昭和20年の敗戦まで「不如帰の時代」は「明治30年代から昭和20年代にかけての5,60年間を指す」p.56と言う。 藤井淑禎(1990)『不如帰の時代』名古屋大学出版会という本があります。そこには後に随筆家として活躍する生方敏郎(1882-1962)の体験記が載っています。
中学校の寄宿舎の中に、紅露の文学を共に談ずる仲間は、両3人を出なかった。しかも「不如帰」を読まぬ学生はただの一人も無かったというとも決して過言ではあるまい。 「明治30年前後ー読者としてー」『早稲田文学』1926(大正15)年1月
私は『不如帰』を完読しましたが、「感動した」という思いは起きませんでした。それもそのはずだと思うのは、今の時代は「戦争」も「結核」も「家族制度」も、「切実な問題」ではないのです。現代から「不如帰の時代」を想像することはなかなか難しいことのようです。
| セル1 | |||||
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から